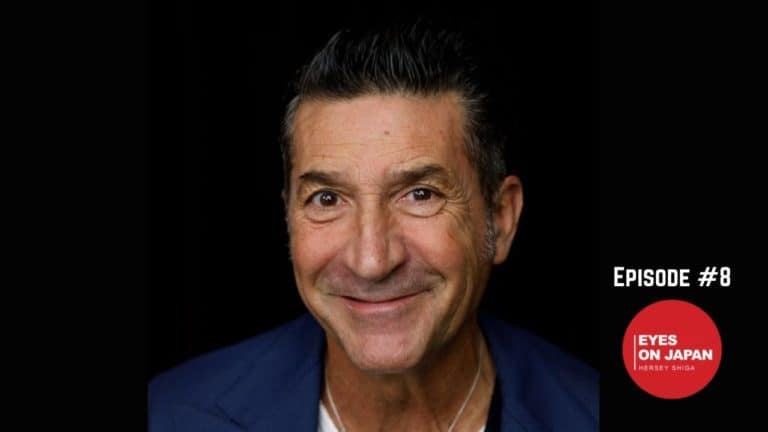日本でチリのオーガニックワインが発売開始 大使館で試飲会開催

チリ共和国大使館では4月1日金曜日にワイン·テイスティング·イベントを開催し、新たにオーガニックのクロ·サンタ·アナ·チリワインを紹介した。
チリのワインに関わる歴史は古く、ワインという存在はチリの文化にも深く根ざしている。チリ大使館では、最近、有機チリワインの輸入が日本市場向けに開始されたことも発表している。
その代表的なワイン、クロ·サンタ·アナ·は、チリのコルチャグア渓谷にあるロベルト·イバラ·ガルシアとルイス·アントニオ·デ·グラシア·アレグレッティが所有するワイナリーで作られている。二人が所有するこのワイナリーは 1.3ヘクタールの広大な土地に、約10,000本のブドウの木が植えられている。このワイナリーからの毎年の生産量は約10,000リットルと少量ではあるが、その品質は最高という評価が与えられている。

ワイナリーのオーナーとして、二人は環境と地元の野生生物を尊重し、強い哲学を持ってほごにも当たっている。また、二人の哲学は、全てが手作りであるというそのワイン生産にも反映されている。作業工程をすべて手で行うことに加え、ワインは土、または樫の木で作られた樽に貯蔵され、発酵の過程を経ていく。こうした作業工程がある為、創り出されたワインは独特で自然な土の風味を持つ。また、二人は、保護犬60匹と保護猫20匹を飼い、10ヘクタールの湿地の管理もし、自然保護に貢献している。
詳細については、同社のWebサイトhttp://winc.asiaをご覧ください。
今回開催されたワイン·テイスティング·イベントでは、赤ワインのシリオス、アラレス、白ワインのベロなどを、ワインに合ったチリ料理、日本料理と共に試飲することができた。これらのワインはすでに2021年12月から日本の市場で入手可能になっており、日本のワイン輸入業者Wからご購入いただける。
クロ・サンタ・アナのワインは、日本の輸入業者「W」よりお買い求め頂けます。
株式詳細についてはこちらをご覧ください。

【関連記事】