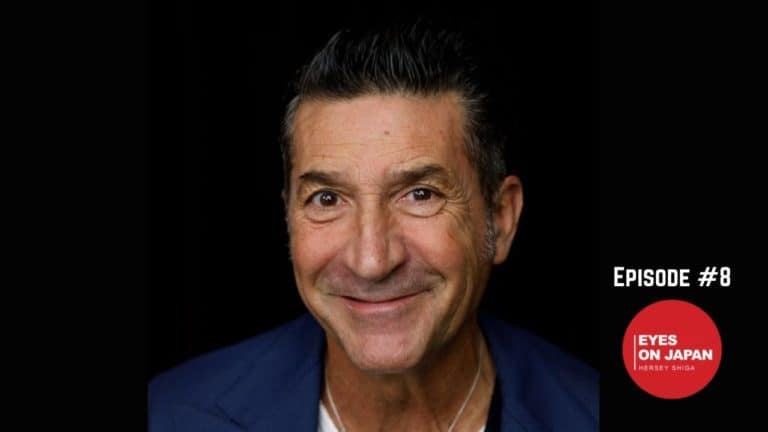マーティン・フラック - 最高級ホスピタリティの達人 –

最高級ホスピタリティの専門家であるマーティン・フラックは、 パーク ハイアット、東京ヒルトン、オークウッドなどのトップクラスのラグジュアリーホテルで20年以上の経験を持つ。そんな、ホスピタリティの達人に、日本が再び外国人観光客へ国境を開くのはいつになるか、そして日本旅行をもっと愉しむ為のヒントを尋ねた。
また、コロナ感染症によってホテル業界が受けた打撃、そして回復の為に行った取り組みについて、更に、日本を旅行する方へ、最高のホテルの見つけ方、日本国内で楽しめるエンターテインメント、日本でトライすべき食についてアドバイス!ホスピタリティの達人ならではの、日本で上質な時を過ごす秘訣が盛りだくさん!
=======
マーティン・フラック(Marin Fluck)について
LinkedIn: https://jp.linkedin.com/in/mfluck